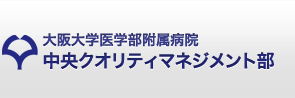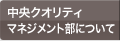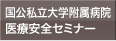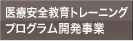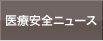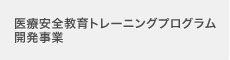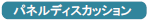学会参加・発表
2025年度
国際学会
| 日時 | 2025年10月23日 |
|---|---|
| 学会名 | The 14th Resilient Health Care Society meeting 2025 (ブラジル、カネラ) |
| 発表者 | 安部猛、永野由美、勝亦秀樹、佐藤仁、中村京太、中島和江 |
| 演題名 | Overcoming ENRYO fosters graceful extensibility: an analysis of team performance in Rapid Response System |
| 日時 | 2025年10月23日 |
|---|---|
| 学会名 | The 14th Resilient Health Care Society meeting 2025 (ブラジル、カネラ) |
| 発表者 | 中島和江、田中晃司、増田真一、安部猛 |
| 演題名 | The dynamic characterristics of verbal interaction among surgical team members duaring robot-assisted esophageal surgery |
| 日時 | 2025年10月23日 |
|---|---|
| 学会名 | The 14th Resilient Health Care Society meeting 2025 (ブラジル、カネラ) |
| 発表者 | 北村温美、黒田真理子、中島和江 |
| 演題名 | A leveraging ICT and connecting silos to create a networking plathome that promotes DEI |
| 内容 | 当院DEIイニシアティブで開発した、多様なキャリア形成支援とワーク・ライフ・インテグレーションの推進を目的とした医師間の情報共有プラットフォーム「アトリエみらいず」を紹介し、期待される効果について報告しました。 |
国内学会
| 日時 | 2025年11月9日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 佐藤仁1,2)、中村京太1,2)、安部猛1,3)、古谷優樹4)、備瀬和也4)、齊藤剛史5)、土屋慶子6) 横浜市立大学附属市民総合医療センター1) 大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部2) 福島県立医科大学 総合科学教育研究センター3) 九州工業大学 大学院情報工学府4) 九州工業大学 大学院情報工学研究院5) 横浜市立大学 都市社会文化研究科6) |
| 演題名 | 麻酔科シミュレーションでの共同的かかわりを可視化する:AI技術を用いた麻酔科医-看護師インタラクションでの共同注視・頭部姿勢検出とその相関性 |
| 内容 | 医療チームが、日々の業務を協力して「うまく」遂行している様子をデータ化して捉えることは、チームが動的な日常の中で安全を生み出すために役立つと考えられます。その手法は、会話分析、画像データ解析、視点解析など様々な方法が考えられますが、本研究では、AIを用いた頭部姿勢推定と特徴点抽出の手法を用い、医療者間の協力的な関わりの一つとして同じものを一緒にみる共同注視を、360度カメラ画像から検出する手法を開発し、精度の検証を行いました。現在のところは、視点解析で抽出したデータと画像データからの検出の相関は中等度(r=0.56)の相関が得られました。数分の動画であっても、チームの行動の解析には膨大な数のデータを処理する必要があり、AI を用いた解析手法の確立は必須です。さらに精度を改善し、注視だけでなく様々な行動を解析できるシステムの構築を今後も進めます。 |
| 日時 | 2025年11月9日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 宇留野達彦1,2)、平野匠1,2)、増田真一3)、峰松佑輔1)、楠本繁崇1)、北村温美2)、中島和江2)、高階雅紀1) 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部1) 大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部2) 大阪大学大学院 医学系研究科心臓血管外科3) |
| 演題名 | キセノン紫外線照射ロボットによる周辺医療機器への影響に関する検証 |
| 内容 | キセノン紫外線照射ロボット LIGHTSTRIKE™(XENEX、アメリカ)は、高強度の紫外線を短時間で照射でき、微生物に対する消毒効果が確認されています。これまで我々は、LIGHTSTRIKE™ の使用が原因と考えられる周辺医療機器(人工呼吸器等)の意図しない動作を経験し、報告してきました。今回、追加検証として、分光照度計を用いて LIGHTSTRIKE™ の分光特性を調査した結果、LIGHTSTRIKE™ は紫外光・可視光とともに赤外光も放出していることが明らかになりました。今回の結果から、赤外光の特性もふまえた遮光を確実に行うことの必要性と、遮光の成否を分光照度計を用いることで評価可能であることが、示されました。 |
| 日時 | 2025年11月9日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 北村温美 |
| 演題名 | 食物の禁忌・アレルギー等情報の共有における留意点と、活用のための考え方 |
| 内容 | 現在厚労省で進められている「電子カルテ情報共有サービス」において、全国で共有すべき食物アレルギー等情報の「項目範囲、粒度、宗教・信念・嗜好の考え方、科学的根拠の考え方」等について、厚労科研滝沢班で検討を重ねた結論を説明しました。 |
| 日時 | 2025年11月9日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 德平夏子 |
| 演題名 | 小児重症例での安全の取り組み・課題:院内搬送について |
| 内容 | 小児医療は個別性の高さ、多様性があり、そのため医療全体の中において必要以上に孤立化している可能性があります。また小児医療の現場はさまざまであり、現場それぞれの課題を抱えながら、多様な患者さんに向き合い日々臨床に取り組んでいます。今回、小児集中治療を対象としたパネルディスカッションを企画し、その中のテーマの一つとして挿管人工呼吸管理中の患児の院内搬送についてとりあげ、ICU管理中と院内搬送中では状況が異なること、そのために注意すべき点について発表しました。 |
| 日時 | 2025年11月8日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 新開裕幸1)、勇佳菜江1)、德平夏子1)、北村温美1)、中村京太1,2)、中島和江1) 大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 医療の質・安全管理部1) |
| 演題名 | 病院新棟におけるシミュレーション訓練を通じたキャパシティ向上の試み |
| 内容 | 当院では、外来・手術部門を集約した新棟の稼働に伴い、従来の急変対応体制では課題が生じる可能性があり、多職種で机上訓練と現場シミュレーションを実施しました。図面とシナリオを用いた検討に加え、実際の環境での体験を通して、Work-As-Imagined と Work-As-Done の差異に基づく課題抽出を進めました。訓練の結果、「コードブルー放送の聞き取りにくさ」「新棟内の案内・誘導の複雑さ」「環境不慣れによる対応遅れ」の3点が明確となり、放送体制の改善や動線見直し、環境順応を目的とした継続的シミュレーションが必要であると整理しました。多職種で現場に生じうる制約やリスクを多角的に検討し、協働して先行的に急変対応キャパシティを向上させた Safety-Ⅱ の取り組みとして報告しました。 |
| 日時 | 2025年11月8日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 北村温美1)、佐藤仁2)、中村京太2)、安部猛3)、中島和江1) 大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター2) 福島県立医科大学 総合科学教育研究センター3) |
| 演題名 | パンデミックなどの緊急的な状況における薬事行政と市民のリスクコミュニケーションに向けたアンケート調査続報 ~保育園・学校・職場からの情報提供の有用性検討~ |
| 内容 | Covid-19で経験されたようなインフォデミックに備えて、薬事行政と市民の相互理解を得るための情報共有の在り方を、各種アンケート調査で検討してきた結果として、①市民は地域性や個別性に応じた情報を求めていること、②そのため地域のリソース(調剤薬局、学校・保育機関、職場)は重要なヘルスコミュニケーションの場となりうること、また、③これらの情報は家族や周囲への波及効果が期待されることから、地域のヘルスリテラシー向上、感染対応力向上につながると考えられることを報告しました。 |
| 日時 | 2025年11月8日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 勇佳菜江、新開裕幸、上間あおい、德平夏子、北村温美、中島和江 |
| 演題名 | Safety-Ⅱを臨床現場で実践可能とするための、病棟副看護師長を対象とした“医療安全部門一日体験”の取り組み |
| 内容 | 臨床と管理の両面を担う副看護師長を対象に、医療安全部門の業務を体験的に学ぶ「医療安全部門体験プログラム」を実施しました。副看護師長がSafety-Ⅱアプローチをどのように現場で活用できるかを体験的に学ぶ機会となり、医療安全部門と臨床現場が相互理解を深め、協働して医療安全に取り組むための有用な取り組みであることを報告しました。 |
| 日時 | 2025年11月8日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 新谷拓也1,2)、吉田直樹1,2)、滝沢牧子3)、北村温美2)、奥田真弘1)、中島和江2) 大阪大学医学部附属病院 薬剤部1) 大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部2) 埼玉医科大学総合医療センター 医療安全対策室3) |
| 演題名 | 特定機能病院(国公立大学病院)間相互のピアレビュー結果からみえる動向 |
| 内容 | 特定機能病院間相互のピアレビューにおける「未承認新規医薬品を用いた医療の提供の適否等を決定する部門」に関する調査結果について発表しました。対象となった全51病院の総審査件数における医薬品の適応外使用の割合は8割を占めており、審査件数の多い病院においては適応外使用に関する業務負担の懸念が示唆され、リスクに応じた審査プロセスの最適化が課題と考えられました。 |
| 日時 | 2025年11月8日 |
|---|---|
| 学会名 | 第20回医療の質・安全学会学術集会(京都) |
| 発表者 | 新開裕幸、勇佳菜江、德平夏子、北村温美、中島和江 |
| 演題名 | Safety-ⅡでデザインするMACT活動 |
| 内容 | 本院では、モニタアラームの過剰発報による「アラーム疲労」を重要課題と捉え、MACTを中心に多職種で改善に取り組んでいます。アラーム履歴の分析を基盤に、看護師・臨床工学技士・医師が協働し、自施設のリスクを把握して実行可能な対策を検討してきました。また、現場支援として e-ラーニングを活用し、継続しやすい教育体制を整えてきました。本学会では、対応遅れを個人要因とせず、現場の特性を踏まえて組織的に改善する Safety-Ⅱ の視点から、当院での実践を紹介しました。イベント後追いに偏らず、日常業務を俯瞰し安全文化を育む先行的マネジメントの重要性を報告しました。 |